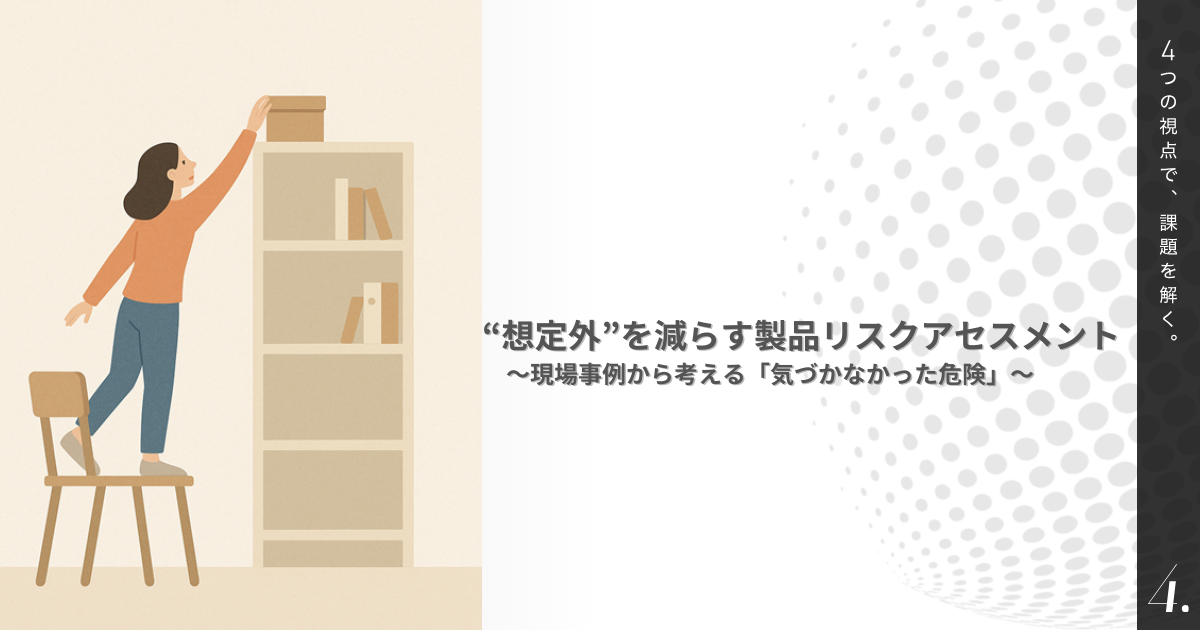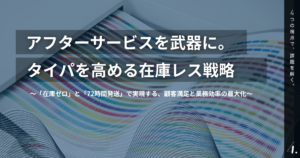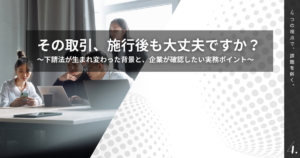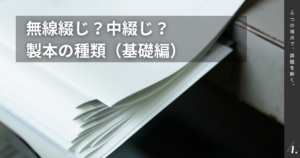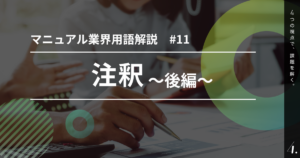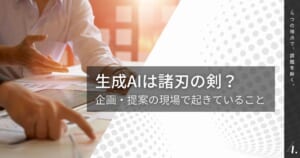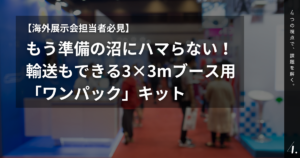製品リスクのご相談をいただく中で、『まさか、そんな使い方をされるとは思いませんでした』という声を耳にすることがあります。丁寧に製品リスクアセスメントを進めていても、思いがけない事故やヒヤリ・ハットにつながる“盲点”に出くわすことがあります。そうした「想定外」がなぜ起きるのか、そしてその見落としをどのように減らすかを、実例を交えながら考えてみました。
1. なぜ「想定外」が起きるのか
第1回「安全とリスク」では、製品の定義や使用条件を明確にすることが「許容できるリスク」の範囲を決める前提であるとお話ししました。これはリスクアセスメントの出発点として、とても重要です。ただし、その前提がどれほど丁寧に決められていても、現実の使用現場では、ユーザーの習慣や環境、製品に対する理解度の違いによって当初の想定を超える状況が生まれることがあります。
例えば、高齢者がガスコンロにかけていたやかんを移動させる際に着衣に火が移ってしまう事故や、介護ベッドの手すりと床板のすき間に手足や頭が挟まる事故などは、製品の想定条件から外れた使い方や環境によって生じています。また、設計者が想定している使用条件をユーザーが十分に理解できていないケースも多くあります。そういった想定外を防ぐ指針としてISO/IEC Guide 51※では合理的に予見可能な誤使用を検討する際には、使用者の属性(高齢者や子ども、外国語話者など)を特定することが求められています。
こうした“想定外”の事例は、前提条件が無意味だったということではなく、むしろ前提条件を定期的に見直し、実際の使われ方やユーザーの特性を反映させる必要があることを教えてくれます。つまり、明確な製品定義と許容リスク設定はスタート地点であり、現場の声や実例を取り入れて繰り返し更新することで、初めて実効性のあるリスク管理につながるのではないでしょうか。
いずれにしても、製品リスクアセスメントの机上では見えてこない「使用者の習慣」「利用環境」「理解度の差異」が重なることで、“想定外”の事故が起きることが分かります。設計者や開発者はこうした実際の事例を踏まえ、ユーザー属性や環境条件を幅広く想定したリスク評価と安全策を検討する必要があります。
※ ISO/IEC Guide 51:2014Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards/安全側面―規格への導入指針
国際規格を起草する際に安全面を盛り込むための共通指針。「安全」を「許容不可能なリスクがない状態」と定義している。このガイドでは、危険源の特定とリスク評価・低減の手順を示し、合理的に予見可能な誤使用を含めたリスクを評価すること、リスク低減の優先順位(①固有安全設計、②安全防護・保護装置、③使用上の情報)を守ることを求めている。
2. よくある“想定外”の現場事例

上のイラストは、椅子の上に立って高いところに手を伸ばす様子を示しています。このような使われ方は製品本来の目的外利用であり、転倒や落下の危険を生みます。こうした事例をいくつか挙げてみます。
・取扱説明書を読まず、独自の方法で組み立てや操作を行ったために機能が十分に発揮されなかった。
たとえば、組み立て式の家具や脚立の説明書を見ないまま自己流で組み上げてしまうと、部品の向きや固定方法を間違えたまま使用してしまうケースがあります。正しい順序やネジの締め付けトルクを守らなかったために、使用中に脚が傾いて折れたり、踏み台が転倒したり怪我をする事故が報告されています。取扱説明書は安全機能が正しく働くように設計者が検討した手順ですから、「読まなくても大丈夫だろう」と自己判断で省いてしまうと、本来の機能が発揮されません。
・工具や機器の部品を逆に取り付けてしまい、本来の安全機構が働かず故障した。
DIYで工具や機械を分解・清掃した後に、部品を逆向きに取り付けてしまい保護カバーが正しく閉まらなかった、という相談があります。安全装置が働かない状態で動かしたことで、刃や回転部がむき出しになり、予期せぬ怪我につながった例もあります。しっかり噛み合わない部品を無理に取り付けると機器が破損し、補修部品や修理費がかさむ結果にもなります。
・高齢者やお子さまが使いやすいようにとご家族が改造を加えた結果、別の危険が生じた。
使用者の身体条件に合わせて工夫すること自体は重要ですが、その改造が安全機能の解除につながるケースがあります。例えば、ガスコンロの油加熱防止装置のセンサー部分に金属板を差し込み火力を強めていたところ、油が過熱し発火した事故が起きています。安全装置を「火力が弱い」と感じて無効にしてしまった結果、本来防げたはずの火災が発生しました。また、高齢の方が旧式の製品に後付けのレバーやスイッチを取り付けた際、部品同士の干渉で思わぬ動作を招いたという報告もあります。
・設置環境が狭く、無理な姿勢で作業せざるを得ず、誤操作につながった。
介護用ベッドでは、ベッド用手すりと床板とのすき間に頭や手足が挟まり窒息や骨折に至る事故が複数発生しています。狭い部屋でベッドを壁に寄せて設置したため、安全スペースが確保できず、介護者が操作パネルに身体を預けた状態で体が挟まるといった「環境側の問題」も背景にあります。作業者が屈んだ姿勢でしかアクセスできないような設置状況だと、手元が見えにくく、ボタンの押し間違いや誤操作が起きやすくなります。製品の設置スペースや周囲の動線を十分に確保することが重要です。
これらはいずれも、設計側では“考えにくい”と思われがちですが、実際に起きています。ユーザーの理解度や使用環境を踏まえた製品リスクアセスメントが十分でなければ、こうした事例は再び発生してしまいます。そこで、日々寄せられる事故情報やクレーム内容をリスクアセスメントの見直しに活かし、「どこまでが許容できる範囲か」「何が合理的に予見可能な誤使用なのか」を継続的に検討していくことが求められます。
※事故事例の参考ソース
・独立行政法人製品評価技術基盤機構 https://www.nite.go.jp/jiko/index.html
・政府広報オンライン 製品・事故:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201409/3.html#:~:text=
・経産省 製品安全ガイド:https://www.meti.go.jp/product_safety/index.html
3. 製品リスクアセスメントを形だけにしないために
製品リスクアセスメントでは、製品がどのように使われるか、どのような危険が潜んでいるかを製品のライフサイクルや危険源のカテゴリーなどから体系的に洗い出します。しかし「ハザード」を列挙するだけでは不十分で、具体的な「リスクシナリオ」として捉えることが大切です。現場で起こり得るシナリオを関係部署で共有し、設計開発担当者だけでなく、営業やカスタマーサービス(品質保証部門)の声も取り入れることで、リスク分析は実効性を帯びます。
製品が実際に使われる現場では、設計開発者が想定していなかった使われ方や環境によって事故が起きることがあります。営業担当者やカスタマーサービスには、そうした「想定外」の情報が日々集まります。営業部門は顧客からの苦情や要望を通じて、どのような使い方がなされ、どのような誤解が生じているかを把握することができます。
これらの情報を「どのようなユーザー」「どんな環境」「どのような操作」が関わったのかという観点で整理し、設計開発の担当者と共有することで、ハザードを単に列挙するだけでなく「実際に起こり得るリスクシナリオ」として掘り下げることができます。たとえば、高齢者向けに火災感知センサーの感度を上げる、介護ベッドの隙間を設計段階でなくす、改造防止の構造にするなど、現場の声を反映した対策が検討できます。
このように、現場で起きた事例を営業やカスタマーサービスと共有し、具体的なシナリオとして捉え直すことが、製品リスクアセスメントを形式的なものに終わらせない鍵になります。またリスクの見落としや想定外を減らすためにも、製品リスクアセスメントを継続的に更新する仕組みも欠かせないでしょう。
1.既存製品のリスクレビューの定期実施
新しいクレームや市場の変化を踏まえ、定期的にリスクアセスメントを見直し、設計やマ ニュアルに反映します。
2.クレーム情報のリスクシナリオ化
お客様からの問い合わせや事故報告を単なる個別事例として処理するのではなく、リスクシナリオの一つとして分析に取り込みます。
3.使用環境・対象者の変化を前提とする思考
高齢者や外国人ユーザーなど、新たな使用者層を想定した分析や、環境が変わっても安全に使用できるような設計を検討します。
4.製品リスクアセスメントは“現場の声”で磨かれる
製品リスクアセスメントは机上の作業だけで完結するものではなく、日々の現場で得られる気づきによって磨かれるのではないでしょうか。製品は販売して終わりではなく、市場販売後も継続して重要な情報を提供してくれます。リスクゼロの100%完璧な商品が理想ですが、市販後のユーザーの環境や使用条件も時間の経過とともに変化がありますので、そういった変化が通常であるという認識で、ユーザーや使用環境の変化にあわせてリスクを、できるだけ定期的に見直しをすることが重要になってきます。
定期的にリアルな声や情報を取り入れながら、使う人と作る人がともに安心できる製品づくりができますよう、製品リスクアセスメントを有効に活用してください。

※挿入イラストは、ChatGPTによる生成画像です。