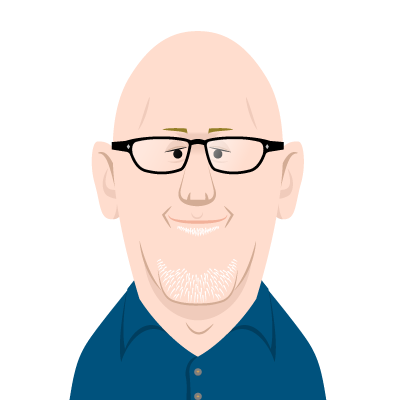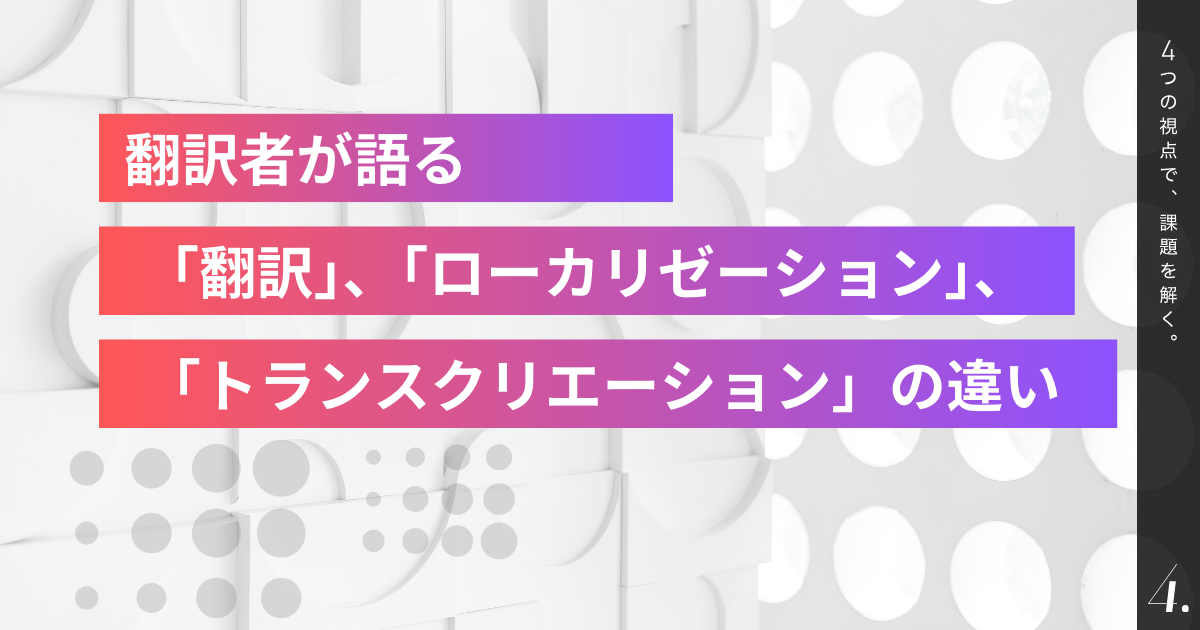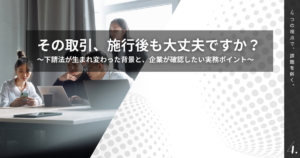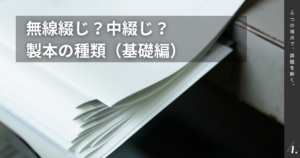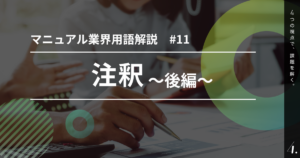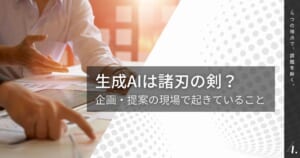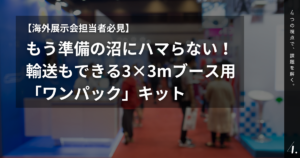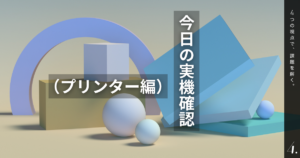「翻訳」だけじゃない!?
ローカリゼーションとトランスクリエーションの違いとは
「翻訳って、ある言語を別の言語に変えることでしょ?」——そう思いますよね。
一見シンプルな作業に思えます。
でも、いざ言語サービスプロバイダー(LSP)に依頼すると、「ローカリゼーション」や「トランスクリエーション」なんて言葉が飛び出してくることも。
「ローカリゼーションはなんとなく翻訳っぽいけど、トランスクリエーションって何!?」と思った方、ご安心ください! 実は、翻訳業界ではテキストの種類や目的に応じて、この3つの手法(翻訳、ローカリゼーション、トランスクリエーション)を使い分けているんです。
この記事では、それぞれの違いをわかりやすく解説し、LSPとスムーズにやり取りできるようお手伝いします!
定義
まずは、基本の定義をチェックしてみましょう。
翻訳(Translation)
ある言語(ソース言語)を別の言語(ターゲット言語)に変換するプロセス。
適切な語彙や文法を使い、原文の意味やスタイル、意図をできるだけ正確に伝えることを重視します。
最もシンプルで、原文との対応関係がはっきりしている方法です。
ローカリゼーション(Localization)
翻訳に加え、コンテンツや製品、サービスを特定の地域や文化に合わせて調整するプロセス。
単位や通貨、日付のフォーマットの変更、現地の規制への対応、デザインや画像の文化的な調整などが含まれます。
ターゲットの文化に自然になじむように仕上げることがポイントです。
トランスクリエーション(Transcreation)
オリジナルのコンテンツを、ターゲットとなる国や地域のネイティブスピーカーに響くよう、創造的にアレンジするプロセス。
「キャッチコピーのような翻訳」とも言われ、ただ訳すのではなく、文化や感情に寄り添った新たな表現を生み出します。
トランスクリエーター(トランスクリエーションの専門家)が、ブランドのメッセージや意図を大切にしながら、より自然で魅力的なコンテンツを作成します。
以下の表では、翻訳・ローカリゼーション・トランスクリエーションの違いをわかりやすく比較しています。
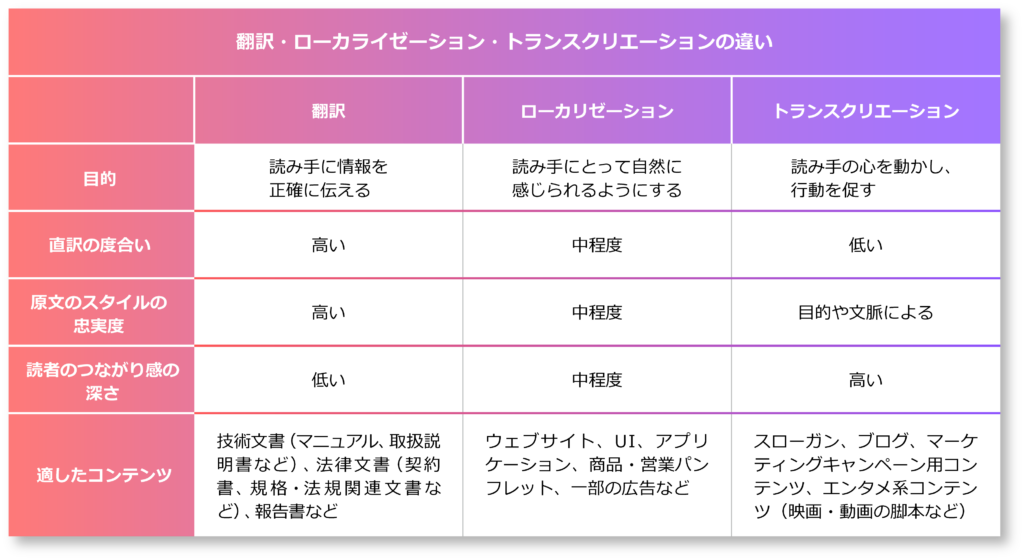
翻訳について
ビジネスで翻訳が必要になるのは、こんな場面です。
- ソース言語のテキストをターゲット言語に正確に変換したい
- 技術情報や指示など、明確なコミュニケーションが求められる
- 論理的・手順的で、繰り返し使われる文章を扱う
- 原文の意味やスタイルを忠実に伝える必要がある
翻訳のシンプルな例
例えば、消費者向け製品の取扱説明書から一文を取り上げてみましょう。 この例では、日本語がソース言語、英語がターゲット言語です。
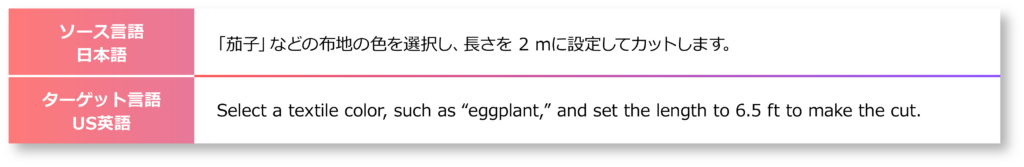
この文章は、ユーザーがアプリを使って生地の色を選び、希望の長さにカットする手順を説明しています。
原文は論理的で、文脈から読み取るニュアンスはありません。
英語訳でも、原文の意味や構造をそのまま再現し、「選択」や「設定」など手順書内で繰り返し登場する単語を適切に訳しています。
このようなテキストこそ、翻訳に適した内容と言えるでしょう。
翻訳が必要な主なコンテンツ
翻訳の対象となるのは、以下のようなものです。
- 技術文書(マニュアル、サービスマニュアル)
- 法律文書(契約書、規格文書)
翻訳の方法
翻訳には、いくつかのアプローチがあります。
- 人間翻訳(HT)
- 機械翻訳(MT)
- 生成AI翻訳(GenAI)
※HT、MT、GenAIの違いについて詳しく知りたい方は、のぶさんの記事「機械翻訳と翻訳者(人間翻訳)の使い分け」をご覧ください。
ローカリゼーションについて
ローカリゼーションとは、特定の国や地域に合わせてコンテンツを最適化することです。
特に、以下のようなケースで重要になります。
- 地域ごとの情報が含まれる場合
(住所、連絡先、ウェブサイトのリンク、各国の規格 など) - 単位が異なる場合
(長さ、重さ、通貨、日付の表記 など) - スペルや語彙、句読点、慣用表現が異なる場合
(アメリカ英語とイギリス英語、スペインのスペイン語とメキシコのスペイン語 など) - 文化的なニュアンスを考慮すべき場合
(ウェブサイトの色使い、シンボル、マスコット、各国の祝日 など)
ローカリゼーションの具体例
実際に、ローカリゼーションがどのような影響を与えるのか見てみましょう。
アメリカ向けとイギリス向けのマニュアルでは、単位やスペルがどのように変わるのでしょうか?
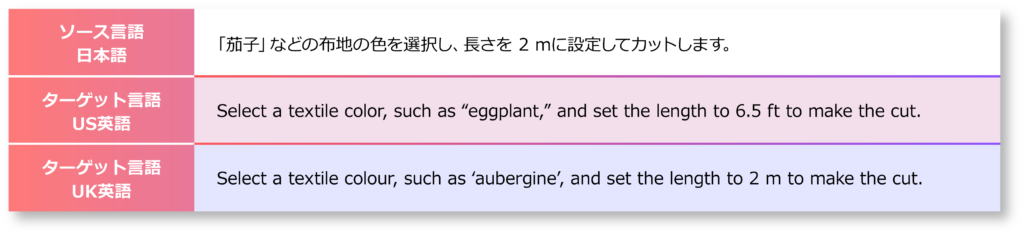
原文(日本語)が一番上、アメリカ英語版が真ん中、イギリス英語版が一番下に配置されています。
どんな違いがあるでしょうか?
- スペルの違い
「色」はアメリカ英語では 「color」、イギリス英語では 「colour」になります。こうした違いは意外と多くあります。 - 語彙の違い
「茄子」は、アメリカ英語では 「eggplant」、イギリス英語では「aubergine」になります。地域ごとに異なる単語が使われるため、翻訳時には注意が必要です。 - 単位の違い
アメリカでは「フィート(ft)」、イギリスでは「メートル(m)」が一般的に使われます。 - 句読点の違い
アメリカ英語では「ダブルクォーテーション(“ ”)」、イギリス英語では「シングルクォーテーション(‘ ’)」が一般的です。 - 引用符の違い
フランス語では「ギュメ(« »)」 が使われるなど、言語ごとに表記ルールが異なります。
ローカリゼーションは、ただの翻訳ではありません。 ターゲット市場に合わせて、コンテンツを 最適化 することが重要です。
文化が違えば、情報の伝え方も変わります。 例えば、日本の消費者は カラフルで情報が多く、画像や選択肢が豊富な広告 を好む傾向があります。
また、色の印象も国によって大きく異なります。 赤色は、ある国では「お祝い」や「幸運」を意味する一方、別の国では「危険」や「怒り」をイメージさせることも。
こうした文化的な違いは、ウェブデザインやマーケティング、さらにはレイアウトやビジュアルの選び方にも影響します。
では、実際に アメリカと日本のスターバックスのウェブサイト を比較してみましょう。
アメリカのスターバックスサイト
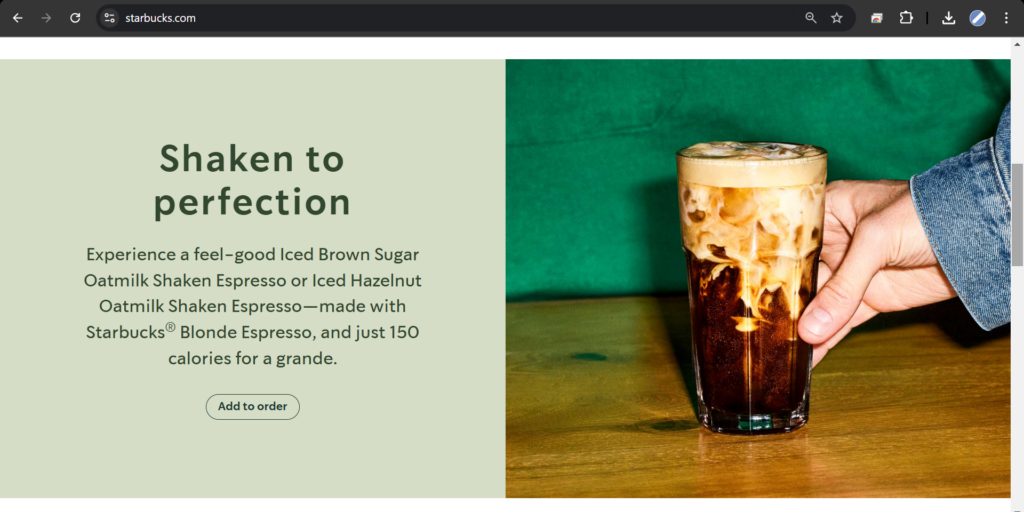
アメリカのスターバックスのウェブサイトは、とても シンプル。
限定メニューの紹介ページでは、テキストは最小限で、余白をたっぷり確保。 ブランドカラー(緑・黒・白)を基調とした落ち着いたデザインが特徴です。
さらに、「注文に追加する(Add to Order)」ボタンが大きく配置され、すぐに注文できる仕様になっています。
シンプル & ストレートなデザイン は、アメリカのマーケットでは一般的です。
日本のスターバックスサイト

一方、日本のサイトは 情報たっぷり&カラフル。 限定メニューのページには、鮮やかな画像と 詳しい商品説明 がずらりと並びます。
さらに、 季節感 も演出。 春なら 桜 のデザインが加わり、3月には 卒業プレゼント の特集が登場。(アメリカの卒業シーズンは6月なので、これは日本独自の要素)
もうひとつ大きな違いは、購入ボタン(CTA)の扱い方。
アメリカ版とは違い、日本のサイトでは 直接的な「購入」ボタン をあまり強調しません。 これは、日本の消費者が「押しつけがましい売り込み」を好まない傾向があるためです。
ローカリゼーションの重要性
このように、ローカリゼーションは 単なる翻訳ではなく、文化に合わせた最適化 を意味します。 ターゲット市場の 感覚や好みにフィット することで、より受け入れられやすいコンテンツになります。
ローカリゼーションの方法には、HT(人間翻訳)、MT(機械翻訳)、HT+MTのハイブリッド翻訳 などがあります。適切な対応をするために、LSP(言語サービスプロバイダー) に相談するのも良いでしょう。
トランスクリエーションについて
トランスクリエーションは、ただの翻訳ではなく、ターゲットの文化や感情に響くように、クリエイティブに再構築するプロセスです。
特に、以下のようなコンテンツで効果を発揮します。
1. 共感を生み、心を動かすコンテンツ
- 企業やブランドのスローガン
- ブランド名・商品名
- 広告のキャッチコピー
- スピーチの一部
- マーケティングキャンペーン など
ターゲットに刺さる言葉選びが大切なので、直訳ではなく、感情や意図を再現 することがカギになります。
2. 文化的な背景や高度な言語スキルが必要なコンテンツ
- 言葉遊びやユーモアを含む表現
- 文化の違いで単純な翻訳が難しいもの
- ターゲット言語にない表現や概念
例えば、日本では「青信号」と言いますが、英語では “green light”(緑信号) というように、文化ごとに言葉の捉え方が異なることがあります。
3. 創造力と文章力が求められるコンテンツ
- 文学作品や詩 など
言葉の美しさや響きを大切にするコンテンツでは、単純な翻訳ではなく、同じ魅力をターゲットの言語で表現 することが求められます。
トランスクリエーションの実例
例えば、AppleのiPhoneプロモーション。
米国と日本のApple公式サイトでは、同じビジュアル を使用しているのに、キャッチコピーの翻訳には大きな違いがあります。
これは、単なる言葉の置き換えではなく、ターゲット市場に合わせた最適な表現に作り直されている ためです。
トランスクリエーションの効果
トランスクリエーションを活用することで、ブランドのメッセージをより魅力的に伝え、ターゲットに強く響かせる ことができます。
言葉のニュアンスや文化の違いを超えて、本当に伝えたいことを、自然に、そして心に届く形で届ける。
それが、トランスクリエーションの力です。
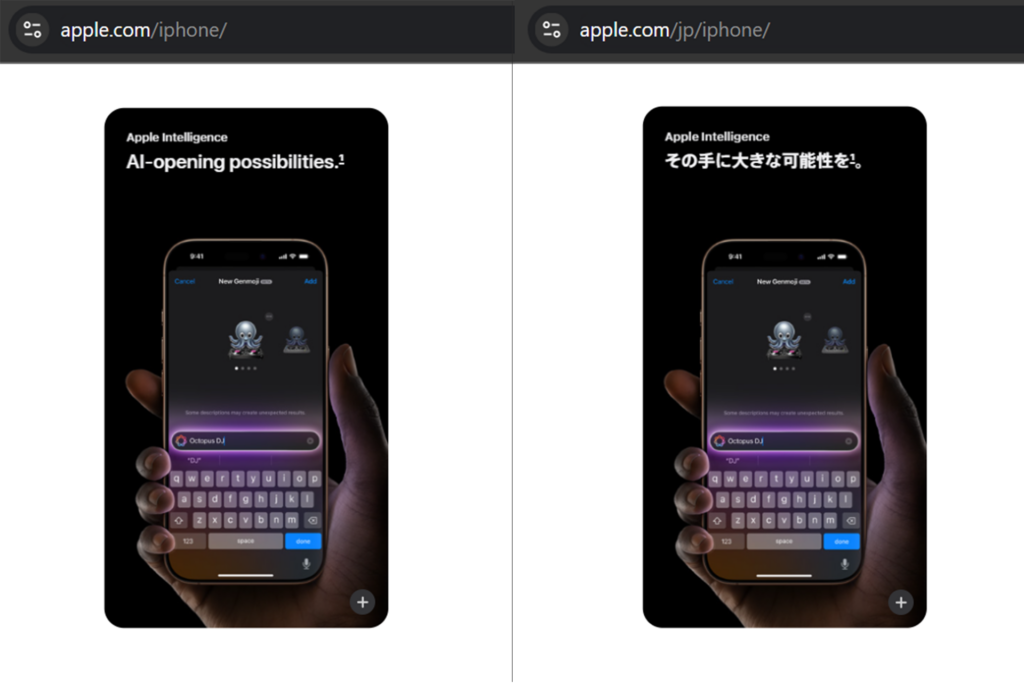
左側の英語キャッチコピー 「AI-opening possibilities.¹」 は、慣用句 「eye-opening」(驚くべき、啓発的な) をもじった言葉遊びになっています。 「eye」と「AI」の発音が似ていることを活かした表現です。
一方、日本語のキャッチコピーは 「その手に大きな可能性を¹。」 となっています。 英語の表現をそのまま訳すと意味が伝わりにくく、不自然になるため、日本語では 自然な響きで、同じインパクトを持たせること が重視されました。
こうした工夫を行うのが トランスクリエーション です。 単なる翻訳ではなく、ブランドの世界観を崩さずに、ターゲットに響く表現を作り直す ことが求められます。
トランスクリエーションにはHT(人間翻訳)が不可欠
トランスクリエーションは 翻訳というよりライティング に近い作業です。 そのため、仕上がりを確認し、何度も調整を重ねる ことが重要になります。
また、コンテンツの種類やボリュームによっては、ローカリゼーションより時間とコストがかかる こともあります。
しかし、ブランドのメッセージを的確に伝え、キャンペーンを成功に導くためには、必要な投資 と言えるでしょう。
まとめ
外国市場向けにコンテンツを準備する際は、翻訳、ローカリゼーション、トランスクリエーション、またはそれらを組み合わせたアプローチが必要になります。
どのサービスが最適かは、目的、テキストの量、締め切り、予算、セキュリティ要件、そして 文化的な知識や創造性の必要レベル によって異なります。
さらに、HT(人間翻訳)、MT(機械翻訳)、GenAI(生成AI翻訳)、MT+HTのハイブリッド翻訳 など、どの手法を選ぶかも重要なポイントです。
クレステック は、翻訳、ローカリゼーション、トランスクリエーション の違いを深く理解し、お客様のニーズに最適な翻訳サービスをご提案します。
これが クレステックの強み です。