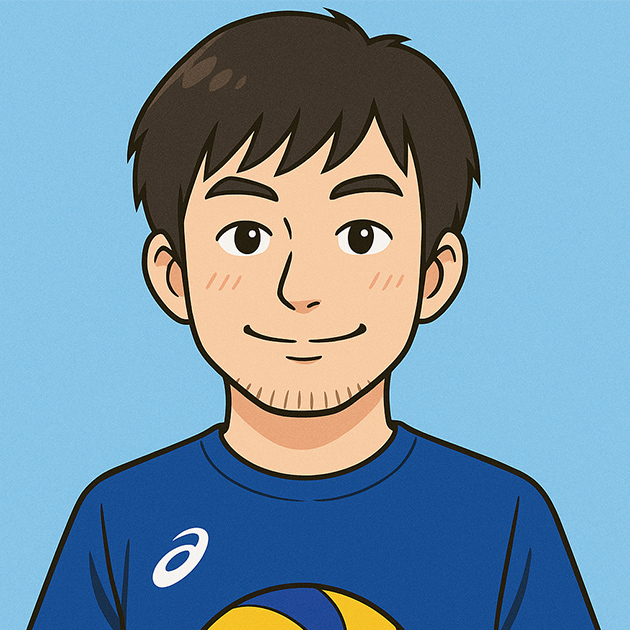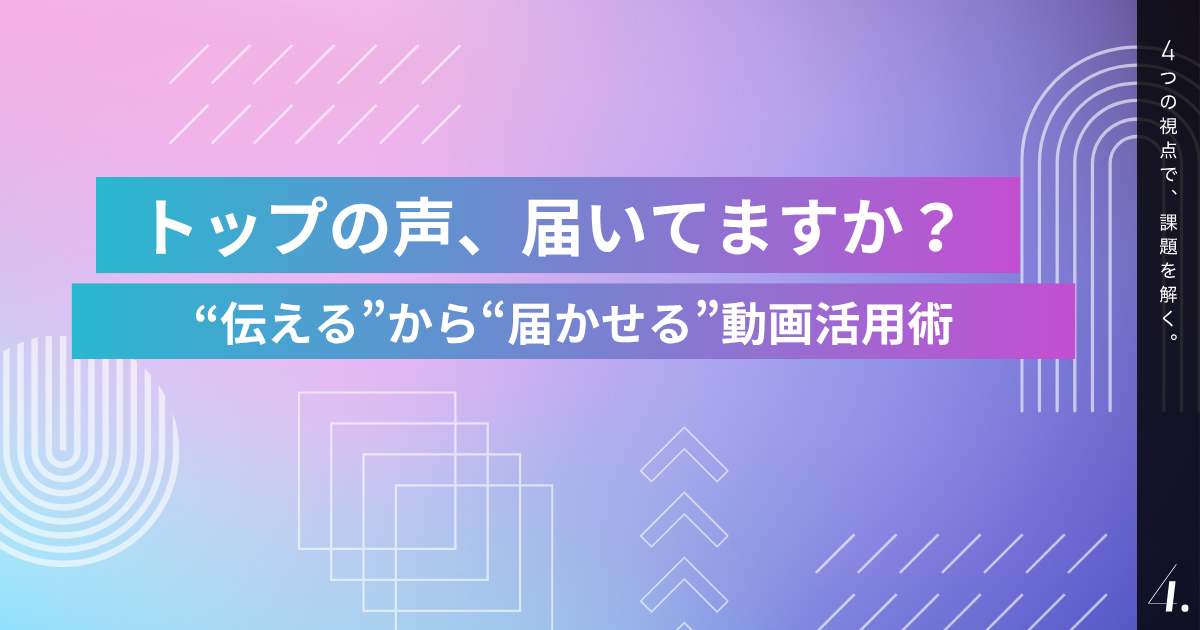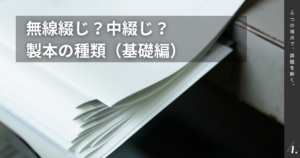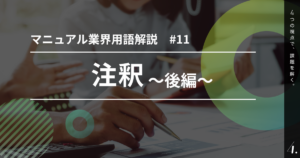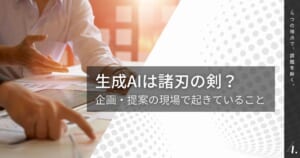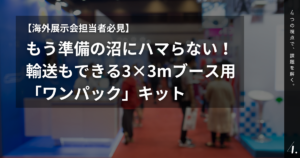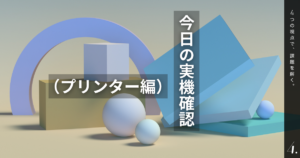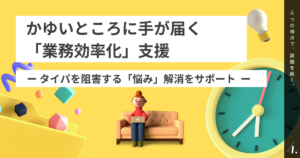企業が掲げるビジョンは、目指すべき未来や社会における存在意義を言語化したものです。社外に向けては、ブランドや信頼性の象徴となり、社内に向けては、従業員一人ひとりの判断や行動の基準として機能します。しかし、そのように重要なメッセージであるにもかかわらず、「なかなか浸透していかない」「伝えているはずなのに、社員からの反応が薄い」といった悩みを抱える企業も少なくありません。実際、私たちが支援する企業の現場からも、こんな声が聞こえてきます。
「社長のメッセージをメールで送ったけれど、読まれていないようだ」
「ビジョン浸透を目的に動画を配信しているが、視聴率が上がらない」
「“共感”してほしいのに、伝達だけで終わってしまう」
これはビジョンに限らず、トップのメッセージ全般に共通する“伝わらなさ”の問題とも言えるでしょう。今回はその課題に対して、「動画」という手段がいかに有効かを、理由とあわせてご紹介します。
経営トップのメッセージが伝わらない理由
私たちは日々、想像以上に多くの情報に囲まれて働いています。メール、チャット、社内ポータル、社内報…。通知が鳴るたびに目を通し、必要な情報を選別し、判断し、行動する。そうした日常が当たり前となった現代の職場では、どんなに重要な情報であっても、埋もれてしまうリスクが高いのです。
社員が経営トップの発信を「読まない」のではなく、「読み切れない」「流してしまう」。
この現象の背景には、情報過多による“情報疲れ”があります。特に働き方が多様化した今、従業員の集中力やリソースは非常に限られています。
さらに、仮に文章が読まれたとしても、そこに込められた表情、声のトーン、抑揚、言葉に詰まる間(ま)といった“空気”は、文字には乗りません。伝わるとは、単に内容が理解されることではなく、共感を生み、記憶に残ることです。その意味で、「何を言ったか」よりも「どう言ったか」が問われる時代になってきているのです。
動画が有効な3つの理由
では、なぜ動画が社内コミュニケーションに適しているのでしょうか。その効果を語る上で、外せない3つの視点があります。
1.非言語情報の豊かさ
たとえば「ありがとう」の一言を伝えるとき。それがどんな表情で、どんな声のトーンで、どんなスピードで語られたかによって、受け手の印象は大きく変わります。
- 真剣な表情で、しっかりと目を見て語られる「ありがとう」
- 柔らかい笑顔で、リズミカルに話される「ありがとう」
- 少し間を取りながら、慎重に選ばれたような「ありがとう」
このような非言語の情報は、文字だけでは決して伝えられません。動画は、その人が“どう語るか”を可視化し、受け手の理解を深めると同時に、感情的な距離を縮める力を持っています。
2.受け取りやすいメディア
動画は、視聴者にとって“受け身”で接することができるメディアです。文章を読むには、時間を確保し、集中し、頭で処理する必要があります。能動的な姿勢が求められる一方、動画は再生ボタンを押すだけ。ながら視聴も可能で、ストレスなく情報を受け取ることができます。
特に1~2分の短尺動画であれば、業務の合間に気軽に視聴でき、「ちょっと見てみようかな」という心理的ハードルが下がります。「社員に時間を割いてもらう」という前提に立てば、文章よりも動画のほうが親切な設計とも言えるのです。
3.時間と場所を選ばない
動画は非同期・非対面での情報伝達が可能です。これは、フルリモート勤務やフレックス制度を採用する企業にとって、非常に大きな利点となります。
全員を集めた説明会の実施が難しい中でも、動画ならスキマ時間で視聴できます。移動中や休憩中、終業後でも、自分のペースで“トップの声”に触れることができるのです。
さらにアーカイブ化すれば、新入社員のオンボーディング資料として再活用したり、過去の発信内容をいつでも振り返ったりすることも可能です。届けるだけで終わらず、“いつでも届く状態”を作れる。これも動画の大きな魅力です。
社内向け動画制作のポイント
動画の効果を最大化するには、社内向けならではの工夫が求められます。以下に、特に重要な3つの視点をご紹介します。
1.つくり込みすぎない
社内向け動画では、自然体が信頼感につながります。完璧な台本を読み上げると、不自然さや“よそ行き感”が伝わってしまいます。キーワードだけをメモにして、自分の言葉で語ってもらうことが、共感を生む第一歩です。
また、撮影環境も大切です。普段の執務室やデスクで、信頼できるスタッフと少人数で撮影すると、緊張が和らぎ、表情や声も柔らかくなります。
編集でも、言い間違いや笑ってしまった瞬間をあえて残すことで、親近感や人間味を伝えることができます。
2.1コンテンツ1メッセージ
伝えたいことが多すぎると、メッセージは散漫になり、結果として何も伝わらなくなります。
たとえば、ビジョンの共有・業績報告・人事施策の説明を一度に語ると、どれも印象に残りにくくなります。
重要なのは、「1本の動画には1つのメッセージ」を徹底すること。動画をシリーズ化して、1回あたりは短く、テーマを絞って発信することで、社員にとっても視聴しやすくなります。
3.コンテンツのバリエーションを増やす
メッセージは繰り返すことで浸透します。同じことを伝えるにしても、表現方法やフォーマットを変えることで、理解と共感は深まります。
- 1分程度の「短尺コメント動画」
- 経営会議や現場視察の様子を伝える「ドキュメント風動画」
- 他部門との対話を通じて語る「クロストーク・座談会形式」
形式を変え、角度を変え、繰り返し伝えることこそが浸透の鍵です。
伝えるのではなく、感じてもらう
経営者の言葉が組織を変えるためには、単に情報を“伝える”のではなく、社員の心に“届く”必要があります。
動画は、そのギャップを埋める有効な手段です。表情、声のトーン、抑揚、言葉に詰まる間(ま)。これらすべてを通じて、トップの人間性や熱量が伝わります。一方通行ではない、“共感”に根ざしたコミュニケーション。それが今、社内で求められているのではないでしょうか。
企画から撮影・編集はもちろん、自社運用ができるようサポートもおこなっています。ご興味ありましたらぜひご相談ください。